女性の力が開花する鍵は、無意識の偏見「アンコンシャス・バイアス」に気づくこと

最初のステップは、バイアスは誰にでもあると知ること
アンコンシャス・バイアスとは、特定の集団・人や物に対する無意識の偏見を指す。ただし、パク氏によると、アンコンシャス・バイアスは誰にでもあるもので、なくなることはあり得ないという。私たちの脳は、いつもスピードと量を求められているからだ。
「人間が何かを判断する方法として、意識的な判断と、無意識的な判断があります。このうち、無意識的な判断は処理速度が非常に速いので、危険な目に遭った時は命を救ってくれることもあるでしょう。また、私たちの脳には絶えず大量の情報が入ってきて、意識的に処理できるのはほんの一部にすぎないことがわかっています」
ただし、スピードと引き換えに、この「無意識」という近道には欠点がある。間違った判断を下しやすいことだ。体験、メディアやSNSの情報、幼少時に言われたことなど、あらゆることから私たちの無意識はつくられ、正しいかどうかを問われる機会は少ない。
「間違ったときに、間違ったと気がつくことが大切なのです。私たちは、偏見をなくすことはできません。でも、それにともなう対応や行動を変えることはできます」
演奏者の姿を隠したオーケストラのオーディション
アンコンシャス・バイアスという概念が、最初に注目された国は米国だ。パク氏は、これはダイバーシティの推進を背景に注目されるようになった概念の一部だという。人種、性別、性的指向など偏見を生む要素をたくさん抱える米国は、長年、ダイバーシティの実現に向けて努力し、一定の成果をおさめていた。ところが、ある程度進むと進歩が停滞し、何か大きな壁があるのではないかと考えられた。
「そのころ、行動経済学者、心理学者たちから『マイノリティの人々が不利になり、活躍できない理由はアンコンシャス・バイアスにある』という研究報告が次々に出てきました。最も有名な報告の一つは、2023年ノーベル経済学賞受賞者のクラウディア・ゴールディン氏によるオーケストラのオーディションについての研究です」
これは、審査員と受験者の間にスクリーンを設置して、審査員が受験者の姿を見られないようにする「ブラインド・オーディション」についての研究だ。この方法では、演奏している人の性別も、肌の色もわからないので、審査員は演奏だけでその人を評価することになる。この方法をとると、女性が審査に合格する比率が大幅に上がった。

「重要なのは、審査員たちが、スクリーンがないときも『私たちは差別はしていない。公平に評価している』と信じていたことです。男性が演奏しているのを見たら、本当により質の高い演奏に聞こえていたわけです」
無意識のバイアスを見事に是正するブラインド・オーディションは、有色人種の合格率も上げた。今ではこの方法は広く普及し、世界各地のオーケストラで団員の多様性を高めている。
名前も、写真もない履歴書で書類審査する
就職面接に欠かせない履歴書にも、アンコンシャス・バイアスにつながる要素がたくさんある。そこで、米国の会社の採用試験ではでは、選考書類の審査員が参照できる情報は限定されていることが多い。
「写真、性別、生年月日、住所、連絡先、通勤時間、扶養家族の有無、配偶者の有無も、評価者が本人の仕事の能力を知るために必要な情報ではありません。氏名も、人種や民族がわかるため、出さないことが多いです」
日本でも、数年前からこうした配慮は始まっている。このような努力は、公平な社会をつくり、個人の幸せにつながるだけではない。
「偏見から解放されれば、適材適所が実現できるでしょう。本当に能力がある人に重要な仕事を任すことは、企業や組織にとって大きなメリットがあります」
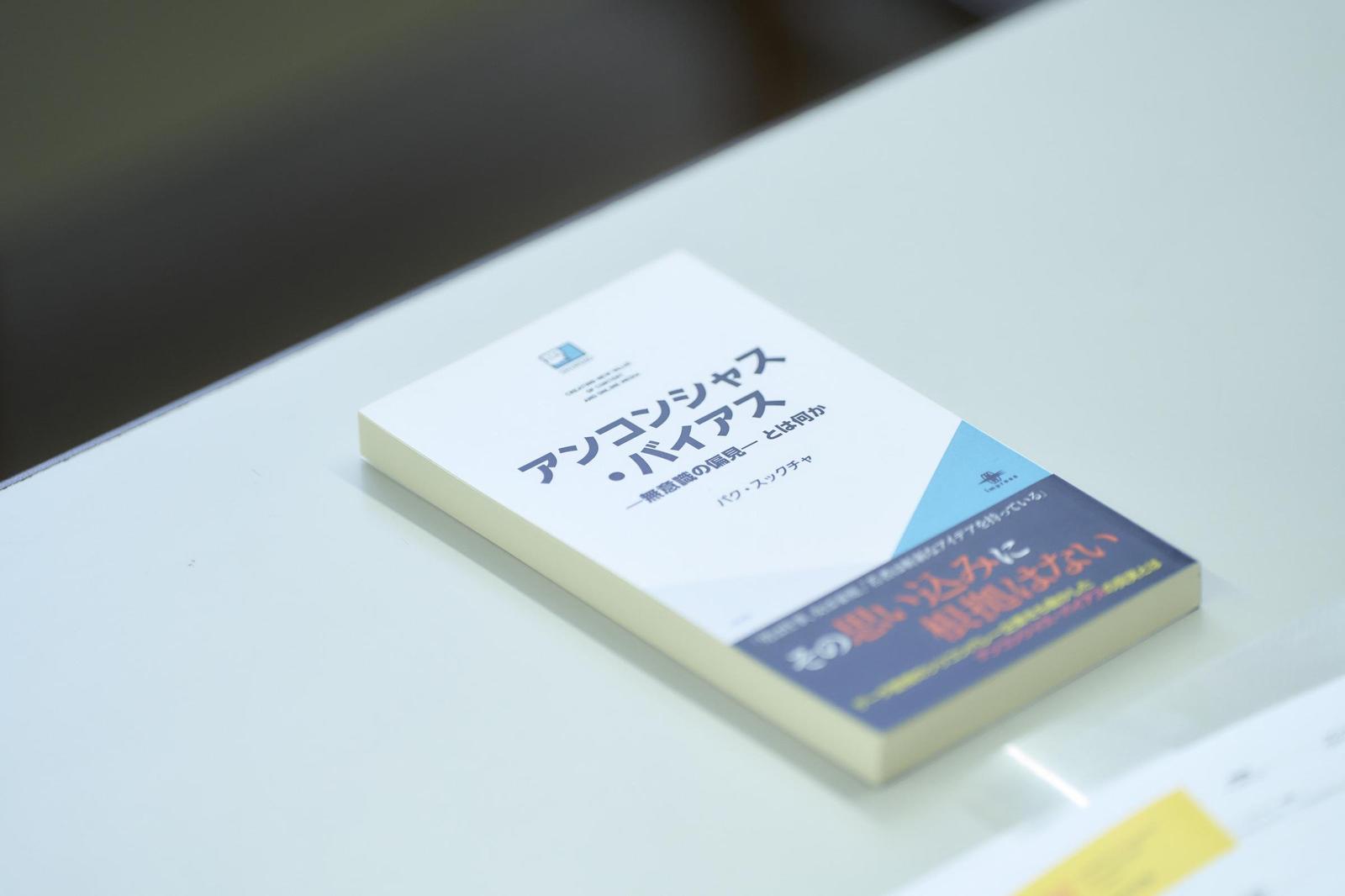
日本の一番の課題は、女性に対するバイアス
パク氏は生まれ育ったのは東京で、家庭には韓国の文化があり、米国に留学し、企業の人材開発などに携わった。3カ国を知るパク氏の目に、東京のダイバーシティはどのように映っているのだろうか。
「日本の一番の課題は、女性へのバイアス」とパク氏は指摘する。特に出産した女性が、性的役割分担意識のために重い負担を背負っています。働き続ける女性が増えたのに、男性の家事・育児時間があまり伸びていません。」
日本では、育児休暇を取得するのはほとんどの場合、女性だけだ。これが「女性は家事、男性は仕事」というバイアスを強めているのではないか、とパク氏は見ている。育休制度が発達しなかったこともあって、米国では、女性労働者が増えると男性たちが家事をするようになったからだ。
「父親にも育児休暇をもっと活用してもらい、育児のスタート地点で家事や育児を担ってもらうことが重要だと思います」
日本の育児休暇の制度は、世界的に見ても整っている。中でも東京都は、育児のために休暇を取得することを「休み」ではなく、社会の未来を担う子どもを育む期間と考え、育休に「育業」という愛称を決定し、社会のマインドチェンジを推進している。こうした変化が進み、女性だけではなく、男性がもっと利用していけば、バイアスの緩和につながるはずだ。
バイアスには、その人のためを思う気持ちから発生する「慈悲的バイアス(ポジティブ・バイアス)」もある。「育児中の女性は大変だから、優しくしてあげたい」と思い、出張がない部署に異動させるといったケースだ。しかし、それは本当の優しさだろうか。
パク氏は、企業にこうアドバイスしている。
「もちろん、配慮は大切です。ただ、育児中の女性一人ひとりがどう感じているかはわかりません。もしかしたら、その女性は育児中もキャリアを積みたいかもしれないし、育児・家事を担ってくれる家族がいるかもしれません。組織は『子どもがいる女性だから、こうだろう』という思い込みで判断せずに、本人と話し合うことが必要です」

女性管理職や政治家は、海外でも少ない国が多いが、日本では特にこの傾向が顕著だ。労働政策研究・研修機構の報告によると、日本で女性が管理職全体に占める割合は12.9%で、米国の3分の1に満たない。ここにも「女性は、リーダーに向いていない」というバイアスが働いている可能性が大きい。
そういった傾向の解消や、誰もが活躍できる社会の実現を目指し、東京都では女性活躍についての検討部会を設置し、条例の制定や女性起業家を支援するセミナーなどを行っている。
「東京が全国の自治体のロールモデルとなって日本中に女性経営者を増やせば、バイアスも小さくなり、女性管理職の増加にもつながるでしょう。東京には全国の大手企業の本社があり、ここまで人材や資金が集中した都市は米国には存在しません」
自分自身に対するアンコンシャス・バイアス
バイアスは、周囲だけではなく、自分自身が持っていることもある。
「私たちは、自分にもバイアスをかけます。そうして、自分のチャンスを、自分で奪っているのです」
「女性だから理系は苦手」「高齢だからITは苦手」などのバイアスを自分自身に対して持っていると、生き方の選択肢はどんどん狭まる。これはキャリアに大きな影響を及ぼし、年収の大きな差となって現れてくる。
「バイアスがあると、チャンスをつかめないだけではなく、本当に能力が下がってしまうこともわかっています」とパク氏は言う。これは、「ステレオタイプの脅威」と呼ばれている現象で、クロード・スティールという社会心理学者がおこなった黒人学生と女子学生の研究で明らかにされた。この研究では、実際は同程度の実力の男女に「女性は数学が苦手」と事前に意識させてから試験を受けさせたところ、女性の点数が低くなった。逆に、苦手かもしれないという不安が解消されると、本来の力が発揮されるという。
「私もバイアスをたくさん持っている」とパク氏は言う。私たちの脳は、たえずバイアスで人や物事を判断し、不要な情報に惑わされて間違い続ける。でも、そのことを受け入れて、思い込みから、その個人との対話へと行動を変えていけば、公平な社会が一歩ずつ近づく。











