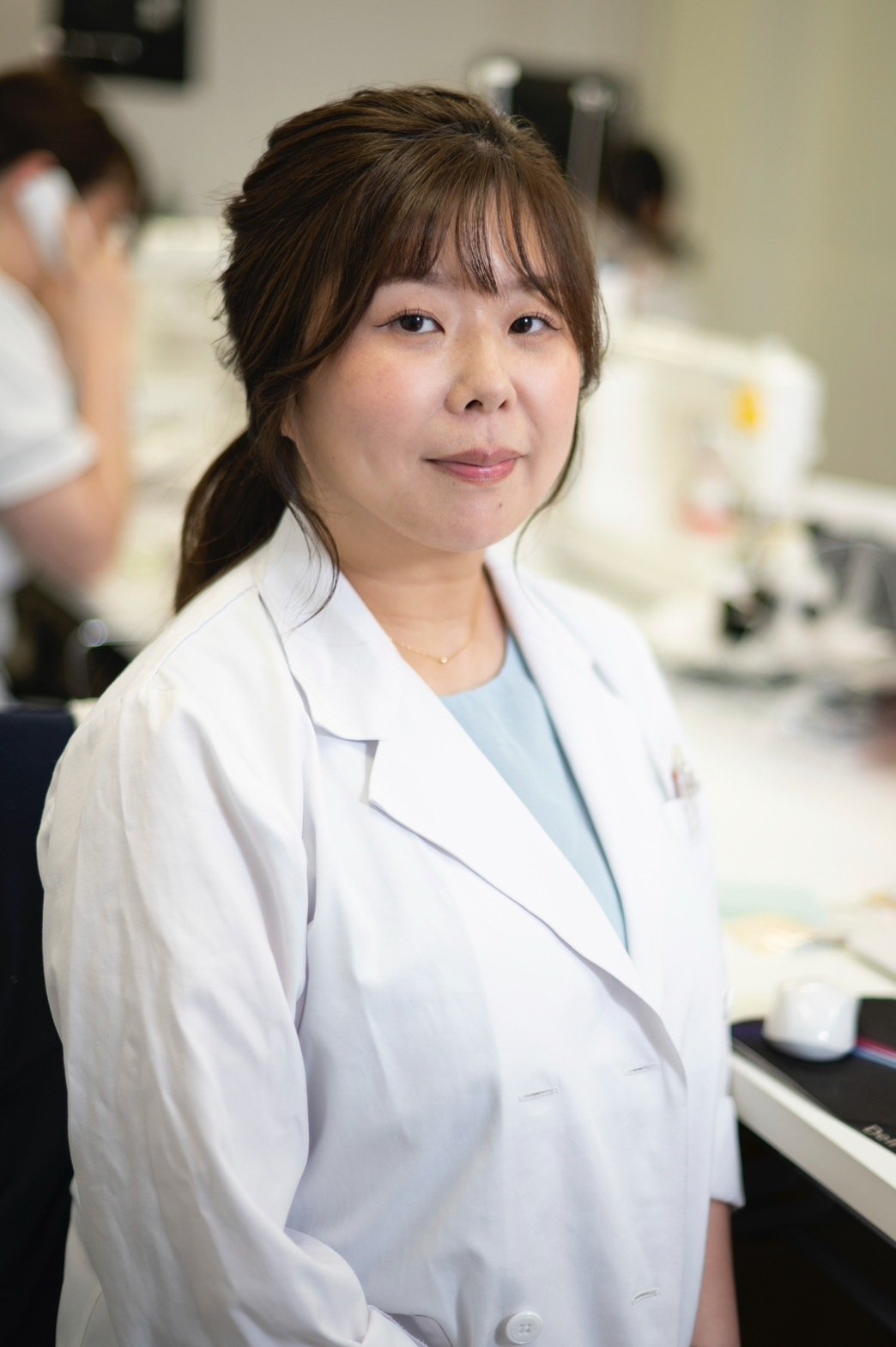ぬいぐるみ専門病院がつなぐ、ぬいぐるみ愛と家族のかたち

洋裁の仕事から、ぬいぐるみ治療の道へ
箱崎氏は、宮城県仙台市出身。幼い頃から祖母に縫い物を教わり、人形の洋服を縫ったりバッグを作ったりしながら、洋裁の道を志すようになった。洋裁の専門学校を卒業後、婦人服オーダーサロンで経験を積み、その後洋服直しの店で働く中で、ぬいぐるみ修理と出会うことになる。
「私が勤務していたお直し屋さんでは、カーテン、テーブルクロス、バッグなど、布製品なら何でも直していました。その中にぬいぐるみの修理メニューもあって、初めてその構造と直し方を知るきっかけになりました」
ぬいぐるみ修理が楽しくなる一方、他の布製品とは異なり、ぬいぐるみは特別な存在だと感じるようになった。きっかけは、直ったぬいぐるみを受け取るときの持ち主が感動する様子だった。
「きれいになったぬいぐるみを受け取ると、お客様はまるで我が子の退院を喜ぶように『本当に良かったね』と涙を流して抱きしめるんです。ぬいぐるみを家族のように大切に扱っている人がたくさんいることを知りました」
ぬいぐるみを大切にする人たちのために自身の技術と経験を活かしたいと、箱崎氏が考えたのが「ぬいぐるみ専門病院」だった。
仙台で開業して2年、東京進出を決意

「ぬいぐるみ専門病院」というコンセプトを固めてから、開業まで約2年の準備期間を要した。ぬいぐるみを直すための技術向上だけでなく、マーケティングやSNSの勉強、経理や税務の知識習得、ホームページ制作の学校に通うなど、箱崎氏はさまざまな知識を身につけていった。
2016年1月、仙台の実家を改装して「杜の都なつみクリニック」を開業。山形県境に近い山奥という立地ながら、主にネットショップを窓口として、全国各地や海外からも依頼が来るようになった。
当時はほとんどが郵送対応であったが、「直接会って話したい」「ぬいぐるみを送るのが心配だから持参したい」とう声も多く、新幹線や電車を乗り継ぎ、遠方からぬいぐるみを連れて来院する依頼者も1割ほどいたという。そして2018年、箱崎氏は大きな決断をする。
「お客様が増えてきて、仙台まで来ていただくのがだんだん申し訳なく感じるようになって。『じゃあ、私たちが一歩近づこう』と、仙台のスタッフ全員を連れて東京に引っ越すことに決めました」
東京が広げたぬいぐるみ治療の可能性
東京進出により、依頼者の約半数は直接来院するようになった。受診の利便性が向上したのはもちろん、ぬいぐるみの治療範囲が格段に広くなったという。仙台では生地やパーツを扱う店が限られていたが、東京に来てからは、新宿の手芸用品専門店や日暮里の問屋街などで、豊富な生地や材料を入手できるようになった。
「週1回は必ず材料調達に出かけています。特に植毛用の毛糸は、ぬいぐるみの部位ごとの日焼け具合に合わせて微妙な色味調整が必要なので、たくさんの素材を直接見て選べるのは大きなメリットです」

治療の幅が広がっただけでなく、東京特有の「ぬいぐるみ愛」に対する寛容なカルチャーも大きな発見だったという。
「東京では、ぬいぐるみ好きであることをオープンにしている人が多くて驚きました。一緒の時間を楽しめるように、ぬいぐるみ用のスイーツを提供するカフェもあります。ぬいぐるみを大切にしている人たちに優しい街だと感じました」
丁寧なカウンセリングが支える専門治療
現在、杜の都なつみクリニックでは、1か月に約100体のぬいぐるみを治療している。治療で最も重視しているのは、客に寄り添う丁寧なカウンセリングだ。
「お客様がどのような治療を望んでいるのか。私たちに何ができるのか。費用はどのくらいになるのか。この三つをしっかり一致させてから治療に入ります。カウンセリングには約2週間かけ、詳細な治療方針を提案し、お客様に選択していただきます」
実際に治療を進める際には、それぞれのぬいぐるみが持つ「個性」を残すことを大切にしている。
「お店に並んだ新品のぬいぐるみは、最初はみんな同じ顔です。その中の一つが家族として迎えられて、長い間を一緒に過ごすうちに、それぞれが個性を持つようになります。表情も変わりますし、日焼けの色あせや使い込んだ風合いも、その子の歴史の一部。お客様と相談しながら、できるだけその子らしさは残すように心がけています」
ある客は、ぬいぐるみについたヒーターのやけどの痕を「これは自分を守ってくれた証」だと、そのまま残すことを希望したそうだ。新品同様に直すのではなく、個性を残しながら元気な状態にしてあげることが、箱崎氏が目指すぬいぐるみ治療である。

ぬいぐるみを通して、自分と向き合う
現代社会における人間関係の複雑さは、誰もが抱える悩みだろう。孤独やストレスを日々感じる私たちにとって、「ぬいぐるみとの対話が心を癒やしてくれる」と、箱崎氏はぬいぐるみがもたらす効果を話してくれた。
「学校でも職場でも、言いたいことが言えずストレスを抱え込んでしまう人が多いと思います。そんなときは、ぬいぐるみに話しかけてみてほしい。触ると柔らかくて、いい匂いがして安心します。私たち人間と同じように、目があって表情があるから、『うんうん』と聞いてくれているように感じるんです」
人が相手であれば当然、何かを伝えるときには「相手はどう思うだろう」と考えてしまい、言えない気持ちや本音を抱え込んでしまうこともあるかもしれない。ぬいぐるみはどんな言葉も受け止めて、どんな時も寄り添ってくれる存在なのだ。
さらに、「自分の言葉で声に出して話すことで、頭の中が整理される」と箱崎氏は語る。ぬいぐるみと向き合うことで、自分自身と向き合い、前へ進むきっかけになるという。

ぬいぐるみの所有に関して、株式会社BANDAI SPIRTSが2025年2月に公表した調査によると、回答者全体の53.8%がぬいぐるみを「10年以上所有している」と回答。性別や年代を問わず、多くの人が長い間ぬいぐるみを大切にしていることがわかる。また、今後利用したいサービスについては、「専門クリーニング」が27.1%、「専門お直し」が17.7%と、ぬいぐるみのケアサービスの需要がうかがえる。
少子化や単身世帯の増加で、家族の在り方が多様化する現代。ペットや観葉植物と同様に、ぬいぐるみを家族の一員として大切にするという選択が、今度も増えていくのかもしれない。
新しい家族のかたちを支える存在として
杜の都なつみクリニックは、2026年に開業から10年を迎える。2025年には、ぬいぐるみ写真集の出版、仙台、名古屋、大阪など国内やシンガポールでの出張診察、YouTubeでの発信など、新しいことに挑戦し続ける箱崎氏。その行動の原動力と、クリニックが目指す未来について伺った。
「特別大きな野心はなくても、やりたいことはなんでもチャレンジして実現してきました。行動すれば失敗することもありますが、良い成果があったことだけを残して、その繰り返しで今に至ります。開業から10年近くたち、5年前、10年前に治療した子が健康診断で再来院してくれることもあります。お客様との信頼関係を大切に、1日でも長くクリニックを続けていきたいです」
杜の都なつみクリニックが提供するのは、単なるぬいぐるみ専門の修理サービスではない。かけがえのない家族の一員への特別なケアなのである。世界に広がる「ぬいぐるみ愛」の中心として、東京という多様性を受け入れる土地で、箱崎氏はこれからも新しい家族のかたちを支え続けていく。
箱崎菜摘美
杜の都なつみクリニック
https://natsumi-clinic.com/写真/穐吉洋子