東京のアナログレコード関係者に聞く。海外のバイヤーは「シーンを支えている」
日本を訪れる何千万もの外国人観光客の間で、自国に持ち帰る土産として最も人気があるものは何だろうか。お茶、お守り、希少なウイスキーなどは根強い人気があるが、最近、訪日客が先を争って買いたがる新たな注目商品がある。アナログレコードだ。ある統計によると、東京はレコード店の数が93軒と世界の首都の中で最多である。また、市場調査会社のIMARCグループ によると、世界のアナログレコード売上高は19億ドルに達している。

日本レコード協会によると、アナログレコードの生産数は2023年に前年から26%急増した。IMARCグループは、この成長が続くと見ており、日本のアナログレコード市場は2024年の8,550万ドルから2033年には1億6,530万ドルに拡大すると予想している。タワーレコードの旗艦店である渋谷店は、こうしたアナログレコードの展望を見越して2024年2月にレコードフロアを改装オープンし、海外からアナログレコードを求めて来店する客の急激な増加に対応するため、売場面積をほぼ2倍に拡張した。
本格的なコレクターやオーディオ愛好家は、以前からお気に入りのアーティストの希少な日本プレス盤を求めてきた。日本製レコードは高品質と考えられており、とりわけ東芝が1958年から1974年に発売した静電気防止剤入りのエバークリーン・レコード、通称赤盤は評価が高い。他にも日本盤の人気の要因として、ジャケットの端に巻かれた日本固有の帯や、中古品の状態の良さが挙げられる。

しかし、近年はアナログレコードのコレクターが、今昔の日本の音楽にもアンテナを広げている。英国リーズにあるCrash Recordsの通信販売担当マネージャーのジョエル・グリーン氏は、まだその魅力はニッチではあるものの、日本の音楽を楽しむ若い消費者が明らかに増えていると話す。
「(日本の音楽を買っているのは)主にソーシャルメディアやYouTubeのアルゴリズムを通じて日本音楽に触れた若者たちです」という。
東京都葛飾区の倉庫を改装して昨年11月にオープンした3,000平方メートルの広大な施設、Skwat Kameari Art Centre内とロンドンに店舗を持つVinyl Delivery Service(VDS)の創業者である関塚林太郎氏も、「NTS RadioやMy Analog Journalのように、人々にもっと多くの音楽を知るよう勧める人もたくさんいます」と語る。
高円寺のUptown Record Storeの創業者であるサッコ・バンゼッティ氏は、「(イエロー・マジック・オーケストラや)坂本龍一などは人気で、常に需要があります。多くの人が80年代ポップス、80年代シンセポップ、ニューウェーブ、シティポップを探しています。これらはトレンドと言ってもいいでしょう。しかし、YouTubeのおかげで、サイケデリックロック、ジャズ、さらに前衛的なアーティストに関心を持つ人もいます」と話す。
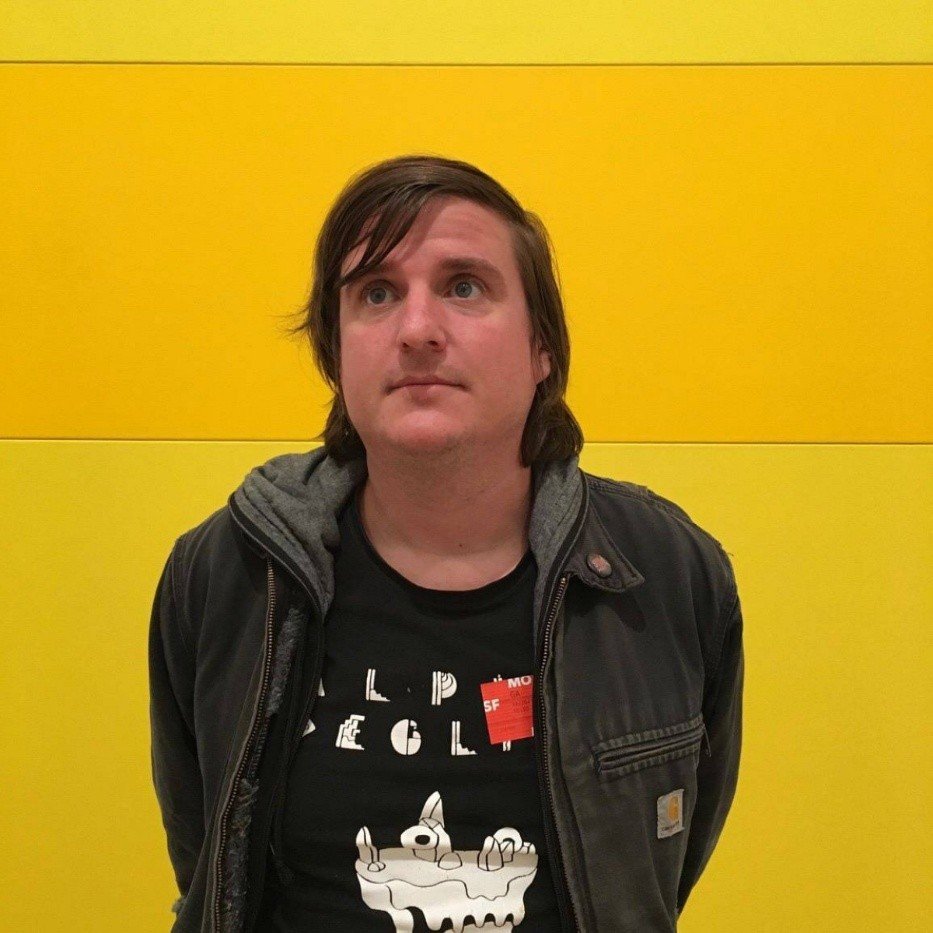
こうした嗜好は、国内のコレクターが購入するアーティストやジャンルとは異なっている。
「かなりの違いがあります」と関塚氏は言う。「70年代、80年代には日本のジャズが大流行したため、多くの優れた作品があります。ロンドン店に置くとすぐに売れてしまいますが、日本では長く店頭に残ります。日本ではレコード店に豊富に在庫があったからだと思います」
関塚氏自身も、海外で日本の音楽への関心を高めるのに大きく貢献している。VDSのロンドン店は、英国初の日本音楽輸入専門店として新たなリスナーを開拓している。
「日本では簡単に手に入るがヨーロッパでは難しいタイトルと共に、希少なレコードも揃えようと考えています。人々は徐々に聴く対象を広げ、さらに深掘りするようになります」

東京に拠点を置くJPvinyl.comの創設者、マシュー・ケッチャム氏も、日本の音楽を広く世界のリスナーに届けるビジネスを手がけている。彼は厳選した日本のアナログレコードのボックスを定期契約者に届けるほか、個人クライアントからの依頼に応じて入手しにくいレコードを調達するサービスを提供している。
ケッチャム氏は「日本郵便を使うのですが、かなり高くついてしまいます。レコード1枚は最大200グラムですが、送料は最低でも3,600円かかるため、私のクライアントはいつも(日本の音楽に)特に高い関心を持っています」と言う。
アナログレコードを取りそろえる実店舗が少なく、送料があまりにも高いため、日本のアナログレコードの世界市場はいまだにニッチにとどまっている。
日本のアナログレコード人気の高まりは、円安や過去最高のインバウンドの波とも関係している。多数のコレクターや転売業者が、この機会にアナログレコードを購入しようとしている。日本の音楽を深く知りたい人もいれば、レコードを持ち帰って愛好家仲間と共有する人もいる。現地価格が手頃なことと国際送料がかからないことが、売り上げの拡大につながっている。

レコード収集とレコード店をたたえるウェブサイト、Tokyo Record Styleの創設者のブライアン・スコット・ピーターソン氏は、「レコード店のオーナーが訪日し、大金をつぎ込んでレコードを買ったとして、そのレコードを持ち帰れば、おそらく1枚で日本への旅費は優にまかなえます」と話す。
有利な為替レートを利用して買付に来る転売業者に対し、日本の中古アナログレコード市場では不快感も生まれている。一部の転売業者が買い付けた後で価格が高騰し、国内のコレクターには手が届かなくなる可能性が生じているのだ。しかし、ケッチャム氏は、インバウンドのレコードバイヤーによる買付が行き過ぎていると不満を抱く人々に対し、強い意見を持っている。
「そのような考えで買付を制限しようとするのは、ビジネスにとって自殺行為です。正しいビジネスのやり方ではないばかりか、音楽は可能な限り誰にでも開かれるべきなのに、人々を音楽から締め出そうとすることになります」

関塚氏も、そのような考えは開かれた市場の現実にそぐわないと言う。
「これが現実の状況です。私はロンドンに店を持っていて、東京にも店を持っているので、違いがよくわかります。市場の価格が違っていて、日本の人が買える価格とヨーロッパの人が買える価格は違いますから、私たちは日本の方が価格が低くなるよう抑えています」
関塚氏はさらに、「私にとっては、お金を稼ぐことが目的ではありません。音楽シーンを支え、音楽を共有することが大事です。さまざまな日本のレコードを輸出すれば、それを人々が聴き、そこからさらに新しい違った音楽が生まれるでしょう。文化は循環するものです。私たちは壮大な音楽の歴史における一つのピースに過ぎないのです」
翻訳/伊豆原弓










