テクノロジーで温室効果ガス排出を追跡するスタートアップが受賞
排出量の追跡
2015年にフランスで設立されたEverimpactは、テクノロジーとデジタルツールを使って、企業や自治体などの組織が自らの温室効果ガス排出量を十分に理解できるようにする。正確なデータがなければ、正味排出量を過小または過大に報告することになり、サステナビリティのために最適な意思決定ができない、あるいはグリーンファイナンスを利用できないリスクがある。
Everimpactは、人工衛星とセンサーを利用して温室効果ガス排出量と炭素フローのリアルタイムデータを収集し、クライアントが気象観測のように排出量の時間的、空間的推移を追跡できるようにする。
CEO兼創業者のマチュー・カルリエ氏は、「当社は世界にカーボンIDカードをもたらします」と述べ、税金など追跡管理が必要な他のシステムでは、社会はすでに固有の識別番号を使用していると指摘する。
Everimpactが日本企業と協力するようになったきっかけは、スタートアップ向けのオンラインアクセラレータープログラムだ。パリのスタートアップキャンパス、Station Fで日本の元経済産業相と面会したこともある。2024年には東京にオフィスを開設した。
カルリエ氏は「日本の人々は、森林の生態系を守り、日本を持続可能な場所にすることの重要性を強く意識しています。未来の成長は環境とテクノロジーから生まれること、この二つを合わせればビジネスの価値を創出できることがわかっているのだと思います」と話す。
Everimpactは、すでに日本の企業や関係先とパイロットプロジェクトを成功させている。
例えば、船舶の排気管にセンサーを取り付け、海上での排出量をモニタリングしているが、そこで驚くべき結果が出た。「船舶の排出量は、これまで考えられていた推定値を約10%下回ることを証明しました」
別のプロジェクトでは、宮城県の森林でカーボンクレジットの量を算出した。このデータは、森林の所有者や関係者が、ダメージを受けた森林の生態系を再生する方法を計画するための基礎となる。カルリエ氏によると、この種のプロジェクトは米国以外では初めてである。
「このプロジェクトの影響力が大きいのは、いくつもの利点があるからです。森林保護に対する経済的インセンティブを生み、炭素隔離により大気中の炭素量を削減し、さらに雇用を創出し、森林所有者にとっては新たな収入源にもなります」
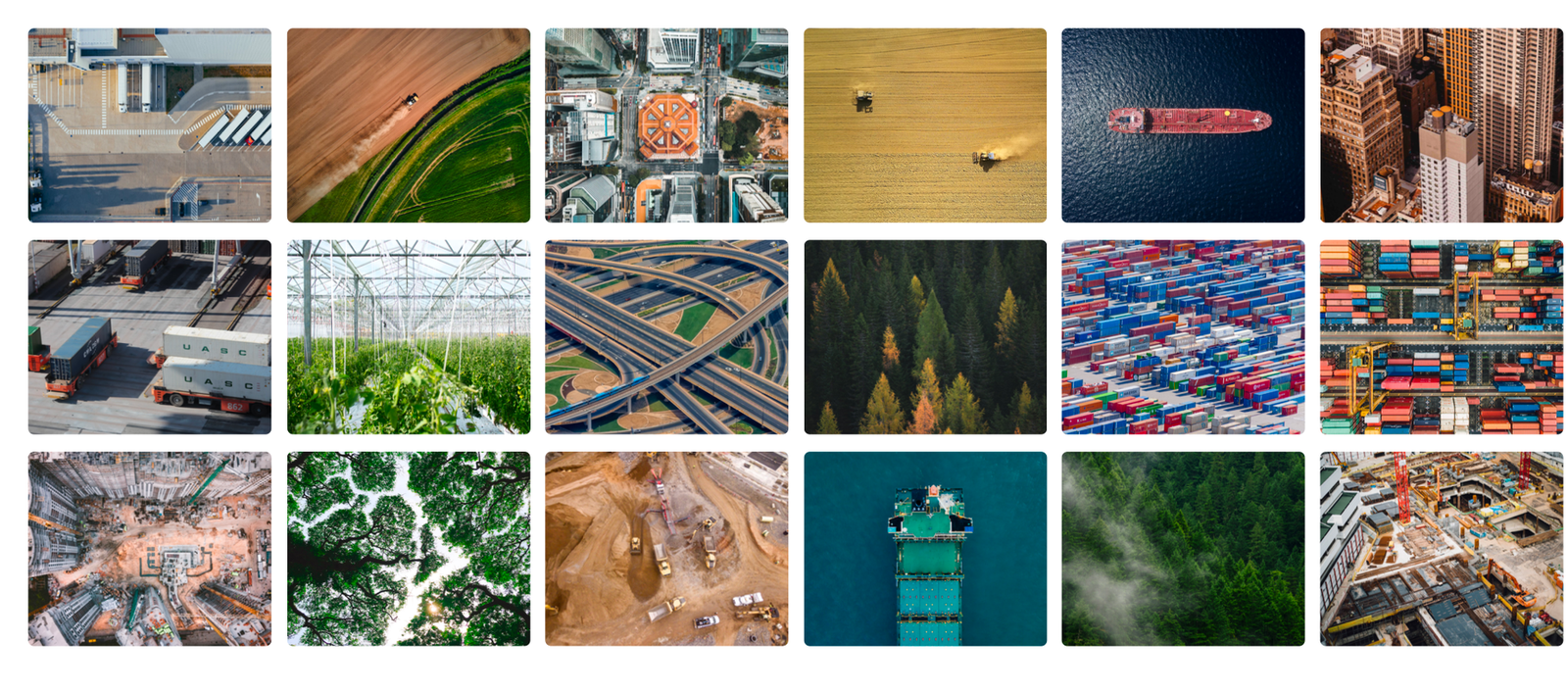
東京金融賞の効果
昨年、Everimpactは東京金融賞2024金融イノベーション部門に応募し、2位を受賞した。
この賞は、アジアのイノベーション・金融ハブを目指す東京都の取組の一環として、金融分野の革新的なソリューションや持続可能な取組を表彰するものだ。金融イノベーション部門とサステナビリティ部門から最終的な受賞者が選定される。金融イノベーション部門については、メンタリングやネットワーキングの機会などの支援プログラムも提供される。
東京金融賞の受賞は、Everimpactに大きな効果をもたらした。「受賞は重要な信頼の証になりました。報道機関や投資家に注目される機会が生まれ、他の国でも信用を得られるようになりました」。カルリエ氏はそう述べて、品質や信用に関して東京と日本の評判が高いことを強調した。
サステナビリティに向けたイノベーションにとって重要な鍵の一つは、企業と銀行とスタートアップの協働であり、大都市東京にはそのすべてがそろっている。「グリーンテックとフィンテックのエコシステム構築における東京の取組は素晴らしく、成熟していると感じます」
信頼性の向上
Everimpactの使命は、排出量について情報に基づくデータ主導の決定を可能にすることだとカルリエ氏は考えている。
それによる重要な効果の一つは、信頼性の向上である。最近は企業などの組織にとって、環境への影響を十分に削減することが極めて重要になっている。良さそうに見えても地球環境への効果がほとんどない取組は「グリーンウォッシング」と呼ばれるリスクがある。
カルリエ氏は「グリーンウォッシングには意図的なものと意図しないものがあります」と説明する。「グリーンウォッシングというと、悪いことをしている者を非難する言葉のように考えがちですが、適切なツールがないためにどこから手を付けてよいかわからないことも、大きな要因の一つだと思います。従うべき基準は多く、収集すべきデータは大量です。人々は途方に暮れ、それによってグリーンウォッシングが起きる場合があります」
Everimpactは、信頼を基盤に、不正確な排出量報告を見つけたら改善しようという考えでさまざまな分野の顧客と協力している。「私たちは、排出量の二重計上や計上漏れといった問題を避けるため、信頼できるデータレイヤーを提供するよう努めています。CO2を追跡することでグリーンウォッシングを減らし、システムの信頼性を向上させます」
Everimpactが事業を拡大し続け、日本の内外で協働するパートナーを増やす中で、カルリエ氏は、カーボンIDシステムの幅広い利用を推進するという同社のミッションを達成したいとし、これが気候危機に対する切り札になると考えている。日本では、東京オフィスの社員数を増やし、アジアで事業開発を続ける拠点とすることを目指している。
最後にカルリエ氏は、「単純なことのように思える時もあるかもしれませんが、私たちは地球と環境について考える必要があります。これらを放置すれば、必ず問題が起きます。わかりきったことなのに、社会として忘れがちです。20~30年後には、排出量1トン当たりの影響がはるかに大きくなるはずです。今行動しなければなりません」と述べた。
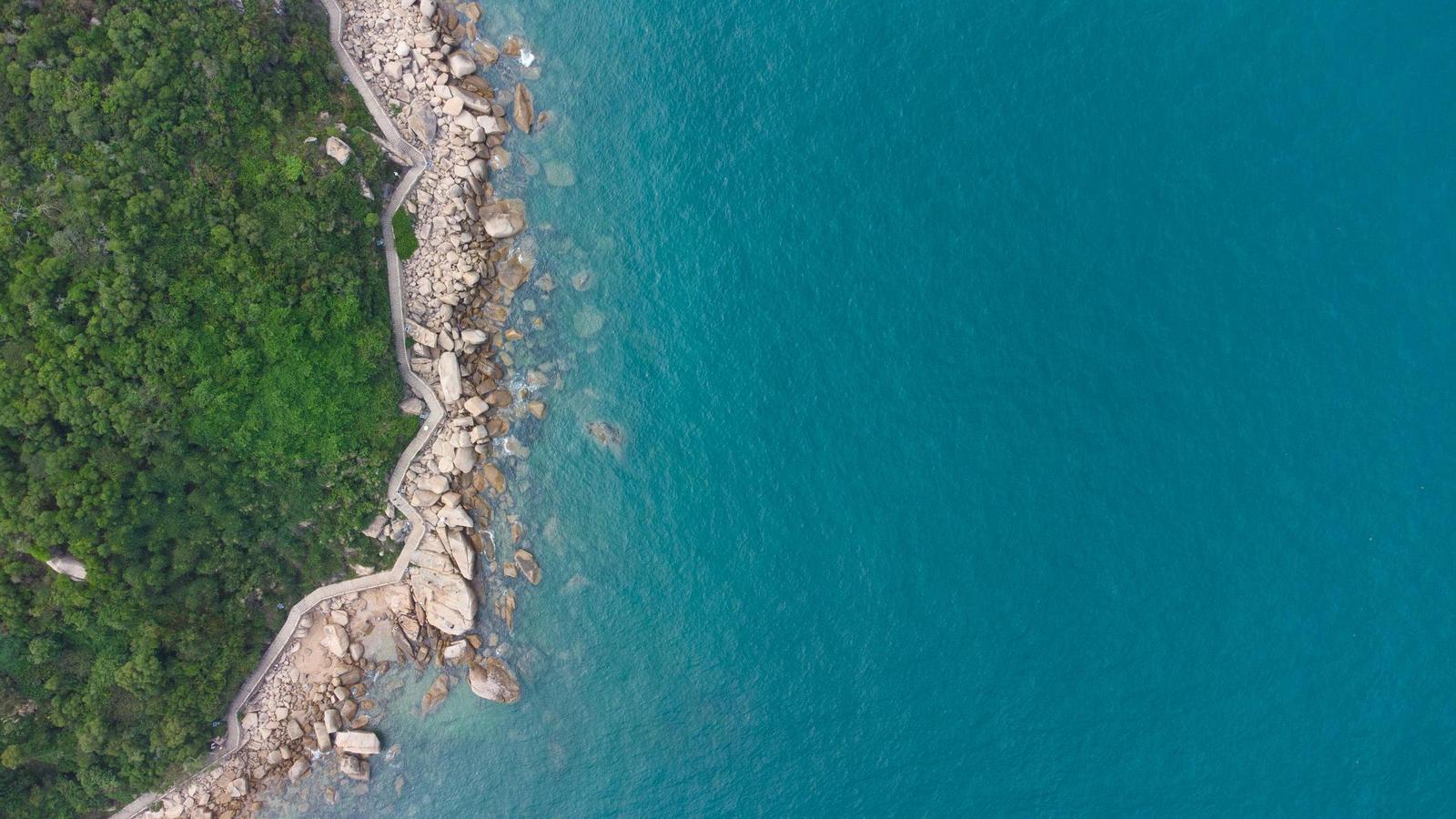
マチュー・カルリエ
Everimpact
https://www.everimpact.com/写真/Everimpact
翻訳/伊豆原弓











