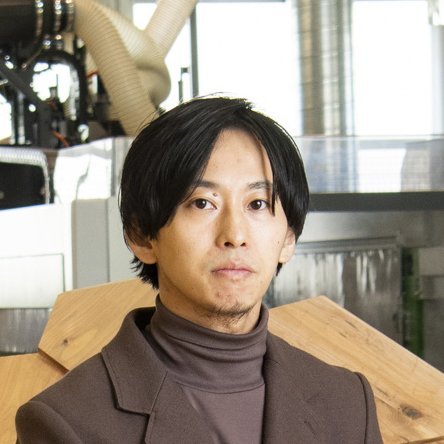「木材で都市の未来を変えていく」(後編)--日建設計・大庭拓也 × VUILD・秋吉浩気、井上達哉

日建設計が手がけた、国際規模のスポーツ競技⼤会施設。外装は、規格品ではなくとも建設時に多く手に入る国産木材を見つけ出し、活用している。
国産材を扱うリテラシー
−−やはり木材を使うなら国産材がいいのでしょうか。
(井上)国産材がスタンダードになるのはまだ難しい。
(大庭)国産材を使った方がいいとは思いますが、どういうやり方で木を調達するかという知識が必要です。日建設計が手がける中大規模の建築で扱う木材は、JAS材や強度などの制約があって使える樹種が限られる上に、一度にものすごい量を使うことになります。伐採計画を考えずに皆伐し(森林の区画にある樹木を全て伐採すること)、切り逃げなんてことになってはいけません。そういった森林側の状況を考慮した「作法」を研究して発信していくのが、組織の中にいる我々の役目だと思っています。
中大規模の建築で扱う木材は制約が多く、割高になってしまうのも事実です。たとえば、不燃木材(不燃の薬剤を注入して製造される木材)をつくるためには、原木3,800円に加工を重ね、100万円/m³になっていたり、歩留まり(1本の原木から作られる木材の割合)が極端に悪くなります。
私が携わった木造建築では、高価な木材を使わずに建てられるような検証方法(耐火性能検証)を用いたものもあります。また、国産材を安定供給してもらうために、建物の概略を設計する基本設計の時点から早めに木材の調達を計画し、発注から納品までの時間の中で、山の循環を崩さず木材が供給されるよう配慮したプロジェクトもあります。
(井上)中大規模の建築のように決められた納期で大量の木材を調達するときに、供給能力を見誤るとプロジェクトの成立が難しくなりますし、地域を混乱させることにもなります。
(大庭)それなら輸入木材で、となってしまいますよね。発注方法を変える必要があります。
(秋吉)だから僕らは、建築家や組織設計事務所が地域の木材を使うためのインフラになりたいと思っています。材料調達と加工をVUILDが担い、設計が変わったらフィードバックをデータで施工者に送る。デザインが変わっても、リアルタイムで納期、伐採計画、金額がどう変わるかわかります。
木材と数十年後の未来

(大庭)カーボンニュートラルの流れの中で、木材はCO2固定(大気や排ガス中に含まれるCO2を木材が吸収し炭素を貯蔵すること)にいいと言われますが、薬剤を含浸させ過ぎて、解体時いきなり産業廃棄物になってしまうかもしません。木材を使おうという段階まで来たのは進歩ですが、ここから先が設計者の腕の見せ所。何も考えずに木材を使ってはいけない。何十年後に解体する時に設計者の腕がわかるでしょうね。
(秋吉)1度でも山に来たら、山の状況がわかったうえでものをつくるように意識が変わるはずなので、そういう機会の提供を増やしていきたいと考えています。木材を使ってみたいと思う人がちょっとでも小さなところから始められるように、現場で実際に作る中で会得していくためのオープンラボ、現場に来てもらうための入り口を極力作りたいと思っています。
(井上)どう実践したらいいかわからないとき、情報や関係を提供するプラットフォームでありたいですね。
(大庭)鉄筋コンクリート造や鉄骨造で建築を考えていたときにはない、木造の素材としてのトレーサビリティやその価値について考えるようになりました。形の背景にあるより社会的な部分での議論が大事だなと。街を考えることは森を考えること、森を考えることは街を考えること、という流れをどんどんつくっていきたいです。
(秋吉)Z世代以降、今後は資本主義とは異なるコミュニズム・アナーキズム的な価値観がデフォルトになっていくでしょうし、身体性やスキルも変わっていきます。20年後、30年後という林業のスパンで考えると、未来は明るいと思います。